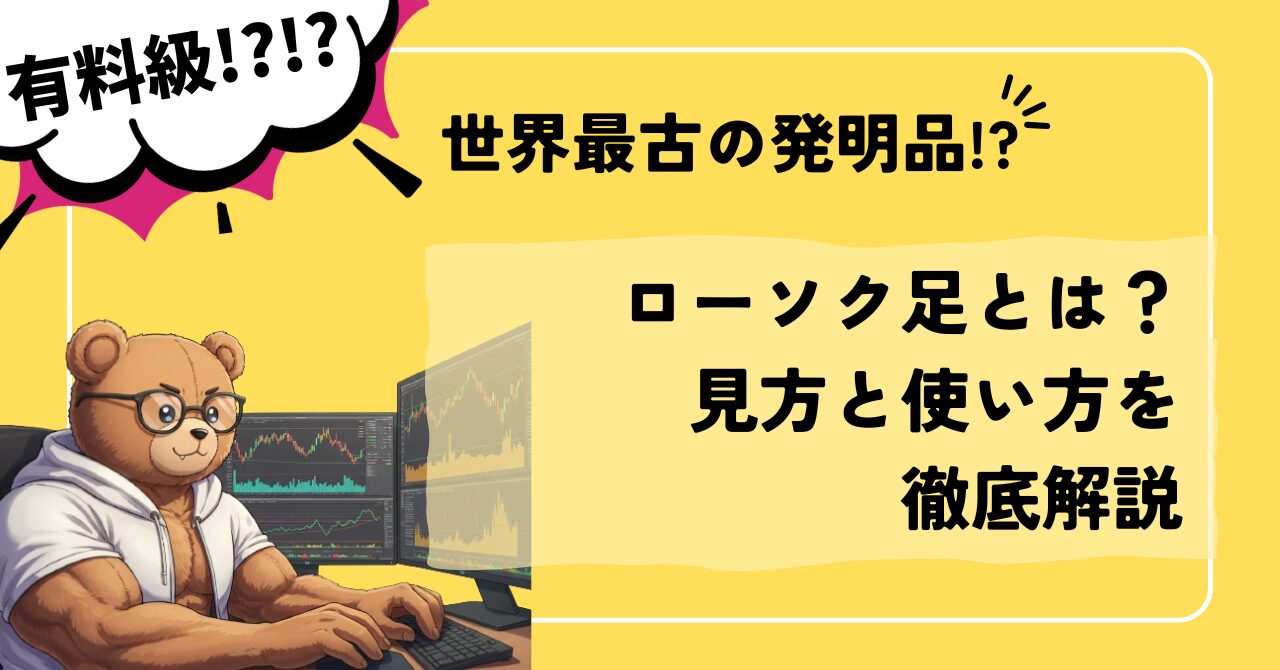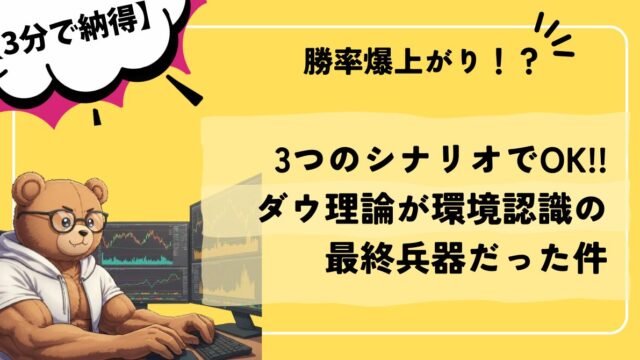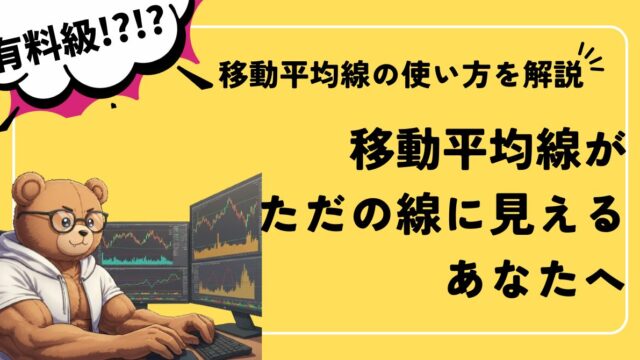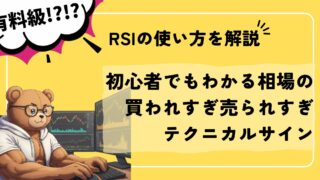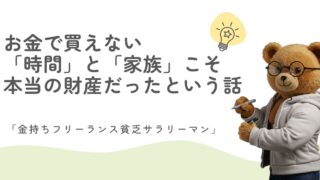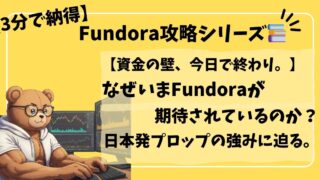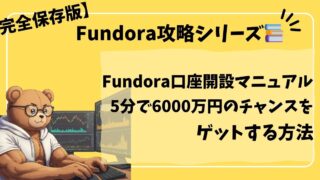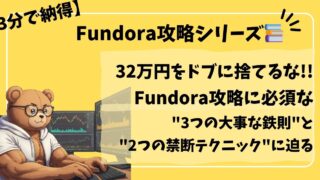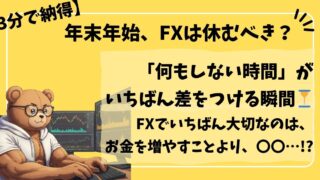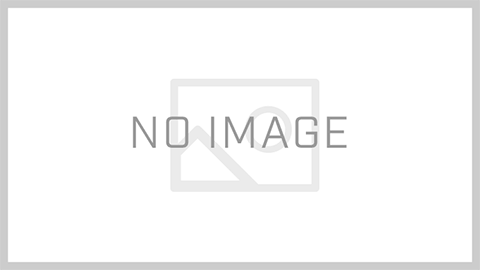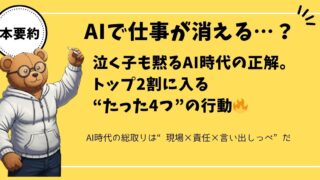「チャートの見方がわからない…」「ローソク足って結局なに?」
そんな初心者トレーダーにとって、最初のハードルが“ローソク足”です。
「なんやこのピコピコ動いてるもんは!!」ですよね?笑笑
ローソク足は、チャートの“言葉”です。
たった1本で、値動きの「始まりと終わり」だけでなく、「勢い」や「迷い」までも教えてくれるんです。
でも、初心者には“ただの棒グラフ”に見えがち。笑笑
だから今日は、「形を見れば今がわかる」チャート分析の第一歩!!
一緒に踏み出していきましょう!
ローソク足とは?簡単にいうと“値動きの絵”
✅江戸から続く発明品?!
ローソク足は、「価格の動き」を1本で表すチャートの基本単位です。
江戸時代から日本で使われてきた相場分析のテクニックで、現在でも広く使われています。
江戸時代には、米相場(特に堂島米相場)で活躍した本間宗久さんという方によって考案され、その後、より洗練された形へと発展したと言われています。
そう、ジャパンメイドなのです!!
✅四本値とは
ローソク足は、1本に4つの情報が詰まっているんです。
- 始値(はじめね)
- 終値(おわりね)
- 高値(たかね)
- 安値(やすね)
この4つの値をもとに、ローソクの“胴体(実体)”と“ヒゲ”ができる。
実体が大きければ「勢いあり」、ヒゲが長ければ「迷いあり」。
つまり、見るべきは「長さ」と「形」なんです。
✅具体例を
たとえば1時間足のローソクなら、その1時間で
・始まりの価格(始値)
・一番高かった価格(高値)
・一番安かった価格(安値)
・終わりの価格(終値)
が記録され、それが“ローソク”の形で表示されます。
見た目は「白黒の棒」や「赤緑の四角」で表示されていることが多いですね。
✅Point(結論)
つまり、ローソク足は“チャートを読むための言語”のようなもので、これが読めるようになると一気に分析が進みます!
ローソク足の基本構造【図で解説】
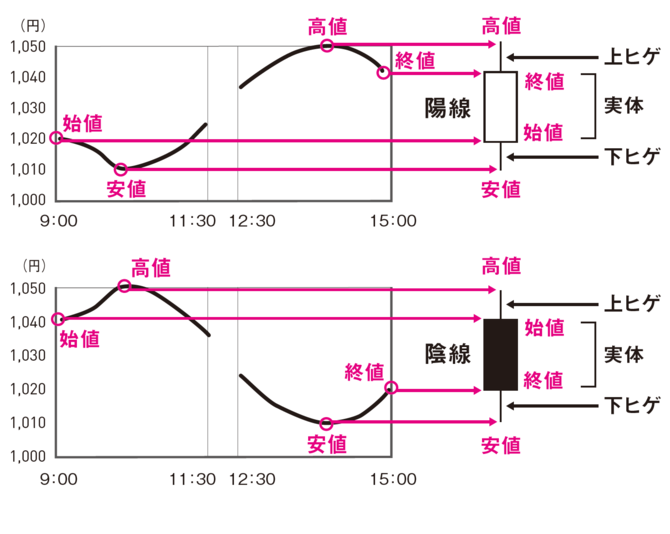
ローソク足は、大きく分けて「実体」と「ヒゲ」の2つで構成されています。
- 実体:始値と終値の差を表す部分(太い部分)
- ヒゲ:高値や安値までの動き(細い線)
【例】
- 終値 > 始値 → 陽線(価格が上がった)
- 終値 < 始値 → 陰線(価格が下がった)
これだけ知っていれば、今後どんなローソク足も読みやすくなりますよ(^^)/
ローソク足の形から読み取れる「心理」
ローソク足の形は、そのときのトレーダー心理を表しています。
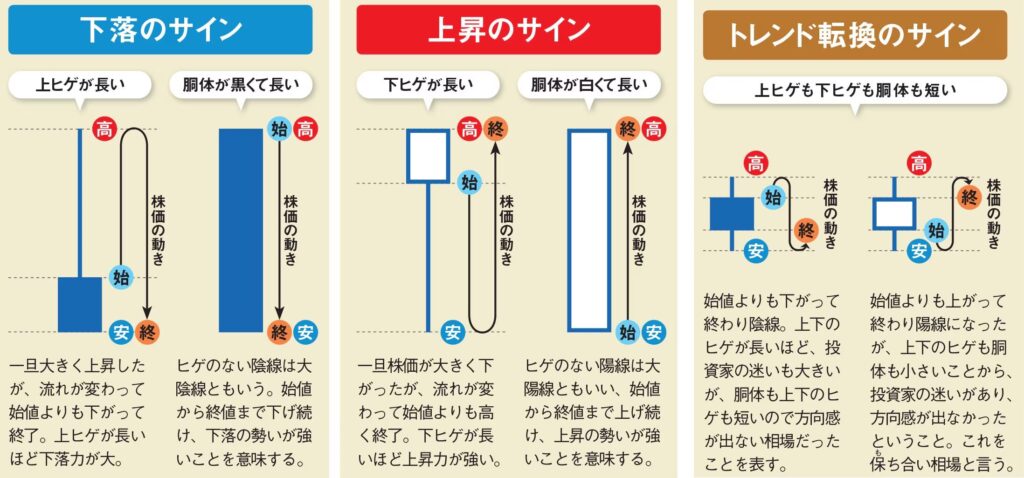
- 長い上ヒゲ → 一時は上がったが、売りが強くて戻された(=上昇の勢いが弱い)
- 長い下ヒゲ → 一時は下がったが、買いが強くて戻された(=下落の勢いが弱い)
- 十字線 → 売り買いが拮抗している(迷いの相場)
こういった“ヒゲ”や“実体の大きさ”から、市場の力関係が読み取れるようになります。
ローソク足をトレードに活かすコツ
- ローソク足1本だけで判断しない
- 複数のローソク足パターンを組み合わせて「流れ」を読む
- RSIや移動平均線など、他のテクニカルと併用する
「ローソク足の形」+「位置」+「他の指標」=勝ちやすいポイント発見!
チャートの“言語”が読めると、トレードが楽になる
ローソク足は、チャート分析の基本であり“世界共通のトレード言語”です。
意味がわかるようになると、チャートがただの線ではなく、「物語」として見えるようになります。
今回のまとめ:チャートは“感情”の集合体
ローソク足を読むことは、「市場の感情」を感じ取ること。
形を知るだけでなく、
“今この瞬間の力関係”を感じられるようになると、トレードの精度が変わります。
ローソク足を知れば知るほど、チャートが話しかけてきます笑笑
まずは毎日、
「今日の一本」に注目して、少しずつ慣れていこう!
初心者でも、この記事を読んだあなたなら、
もう「ローソク足ってなに?」とは言わせませんぞ!!笑笑
「次は“ローソク足パターン”を知りたい!」という声があれば、
続編も用意するので、ぜひコメントくださいね!
ではまた!!